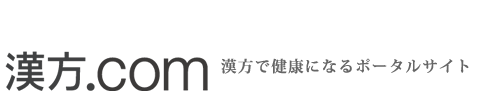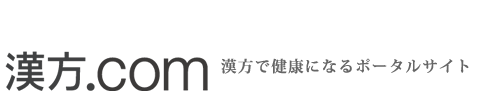「言語障害」といっても、障害を受けた脳の場所によって症状が違ってきます。側頭葉(聴覚、嗅覚、味覚)に障害が現れると、言葉を聞いて理解する力が衰え、相手との会話が成り立たなくなります。情緒や感情の中枢、言葉を聞いて理解する感覚性言語中枢が障害を受けてしまうからです。
このような症状を「ウェルニッケ失語」といいます。 前頭葉(思考、判断、計算)に障害を受けますと、頭では言葉を理解できているのに、話そうとすると言葉にならなくなります。これは「ブローカー失語」といいまして、手足を動かす為の指令を出す運動中枢や、言葉を話す為の機能を調整する運動性言語中枢が障害を受けるからです。
その他にも、言葉を理解することも話すことも出来ない「全失語」、言葉を理解できても簡単な単語を忘れてしまう「健忘性失語」があります。
これらの失語症は、発病後6カ月を過ぎてから回復することもあります。失語症のリハビリは、病状や精神状態が安定してからはじめ、根気よく続けることが大切です。また、舌や喉などの発音に必要な筋肉にマヒがあると、ろれつが回らなくなり言葉がつっかえてしまう「マヒ性構音障害」がおこります。早期から顔や口、舌を動かす練習が必要となってきます。 |