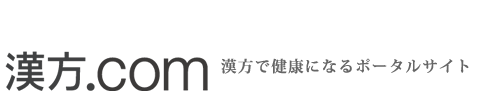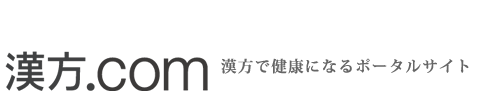|
●検査や治療が行いやすい
|
|
視点 |
利点 |
欠点 |
患者側 |
生理学的 |
| ● |
治療に対して協力的になり、自ら前向きに治療できる |
|
| ● |
不用意に告知すると、患者は混乱に陥り、適切な対処ができずかえって予後を悪くする |
|
|
| 心理社会学的 |
| ● |
家庭や職場などの社会的問題を処理し、身辺整理ができる |
|
| ● |
人によっては闘病意欲を失い、自暴自棄になったり、急に子供のように甘えるなどの退行反応を起こす |
|
| ● |
上手に告知されると、かえって落ち着く患者が多い |
|
| ● |
家族の側からみると、嘘をつかれなくてすみ安心感が得られ、付き添いやすくなる |
|
| 生命倫理的 |
|
|
| ● |
生きてきた証や、ライフワークの完成に努めることができる |
|
|
医療側 |
生理学的 |
|
- |
| |
- |
|
|
| 心理社会学的 |
| ● |
秘密がなくなり、嘘をつく必要がないことで気持ちが楽になる |
|
- |
|
- |
| ● |
告げないことにより生じる、医事紛争などの心配から解放される |
|
| ● |
人によっては告知前より対応が難しくなることがある
(医療側に怒りを示すこともある) |
|
| 生命倫理的 |
| ● |
最後まで充実した生が送れるような治療や、ケアがしやすい |
|
- |
| ● |
患者と医療者関係が、より緊密になり信頼関係が強まる |
|
| ● |
告知後のフォローを十分にしなくてはならない。そのためチーム・プログラムが必要となる |
|